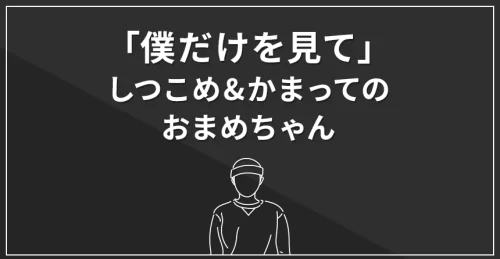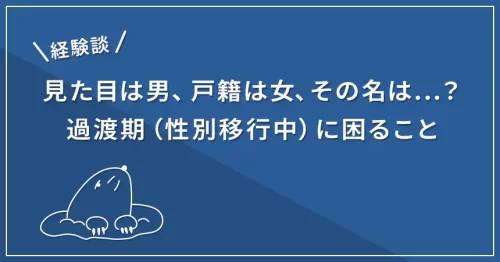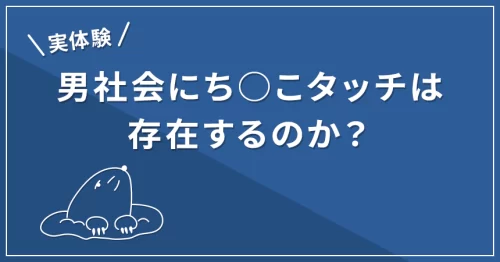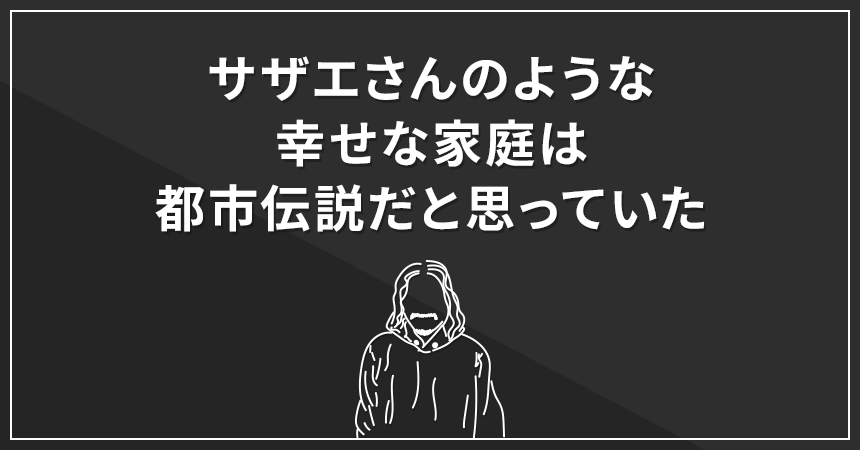
こんにちは、おもちです。
僕は幼い頃、サザエさんのような幸せな家庭は所詮マンガの世界、つまり都市伝説だと思っていた。
しかし成長するにつれ、ある疑念が生まれる。
あれ...?もしかして、現実世界にもサザエさん一家は存在するんか...?
そして、サザエさんは都市伝説ではなかったことに気づいてしまう。
これには、僕の家庭環境が大きく影響している。
就学前の僕は、弟や妹の世話を任され、保育園や幼稚園に行っていなかった。
兄弟の面倒を見ることが、自分の使命だと思っていたのだ。
人生初の盛大な勘違い。
そのため、同年代の友達はいなかった。
そこには、母が産後うつで家から出られなかった背景がある。
母は、徒歩10分にも満たないスーパーへ買い物にすら行けないレベルだった。
食材は生協(コープ)で注文し、近所の集配場所まで僕が取りに行く。
そして、近所のおばさま方の井戸端会議に混ざる僕。5歳。
母は、動きたくても「動けなかった」のだ。
そんな母を、父は「怠け者」と罵った。
当時の母は、自分が産後うつだと思っていなかったそうだ。
もちろん、5歳の僕が、
「おかん、産後うつじゃね?」
と、言うわけもなく。
母も自覚していなかったため、然るべき病院に通院もしていなかった。
「今となっては分かるけど、あの時は絶対うつだった。」
母は最近、申し訳なさそうに話していた。
当時の写真を見れば、母がうつだったことは一発でわかる。
吹き出してしまうレベルで、母の目は死んだ魚の目をしているから。
そんな母は、歳を重ねるにつれ、やかましいほど元気になっているのでなによりだ。
当時の自分の写真を見て「やっばぁ」と言って笑っている。
いつからか、ギャル語も使うようになった。
あっぱれである。
僕たち一家は、父の転勤で田舎から上京。
母は、東京に来てからも次から次へと子どもを産み落とした。
子育てに追われ、目まぐるしく過ぎていく日々。
東京で友達をつくる暇などなかったのだろう。
頼れる親も友達も近くにいなくて、心細かったはずだ。
母の孤独な戦いがどれだけ辛かったのか、僕には想像できない。
一方父は、我が家で絶対的王者だった。
母には言葉の暴力、幼い子どもたちには物理的な暴力で支配した。
波平さんとは一味違う、我が家の勘違い王の爆誕である。
そして幼い僕は、この破綻している家庭環境を「当たり前」だと思い育ってしまう。
一種の洗脳だ。
専業主婦だった母は、経済的な理由から離婚という選択肢は頭になかったという。
そして、幼い僕は「お母さんは1日中寝ている生き物」と認識していた。
兄は小学生で、日中は家にいなかったため、僕が弟や妹の面倒をみなければいけない。
自分のご飯は自分で作り、子分たちにミルクを与え、オムツの交換もしていた。
吾輩は5歳である。
だがしかし、これは必然であり、僕にとって当たり前だった。
そのため、何も疑問に思うことはなかった。
5歳の僕が、1歳に満たないおまめをベビーカーに乗せ、その隣を2歳の妹が歩く。
カオス。
はたから見れば、それはそれは異常な光景だっただろう。
妹とおまめが昼寝をした隙に、家をそっと抜け出し道端でひとり遊ぶのが僕の日課。
近所の子どもたちは学校や幼稚園に行っているため、僕の友達は近所のじぃ様ばぁ様だった。
会うといつもじゃんけんを挑んでくるじぃ様。
バカでかい平屋にひとりで住む怖いばぁ様。
じゃんけんを挑んでくるじぃ様は、「おはよう」「こんにちは」の挨拶を一切しない。
僕を見つけると、「じゃ~んけん...」と、強制的にじゃんけん大会を開催してくる。
じゃんけんが挨拶代わりだったのだ。
僕はそんなじぃ様を「じゃんけんじいちゃん」と呼んでいた。
うろ覚えだけど、じゃんけんじいちゃんの頭はハゲていて、真っ白な髭はサンタクロースみたいに長かった。
いつも作務衣を着ていて、自宅の前で腕を組んで立っていた。
一体、何者だったのだろう。
もしかすると、仙人だったのかもしれない。
じゃんけんじいちゃんは僕をかわいがってくれていたけど、僕の名前を一字違いで記憶していた。
なぜか僕も訂正しなかったため、いつも間違った名前で呼ばれていた。
それでも僕は、じゃんけんじいちゃんが大好きだった。
じゃんけんじいちゃんは、じゃんけんに勝っても負けても飴をくれる。
飴が無尽蔵に、わんさか出てきた。
しかし僕の目的は、飴をもらうことではない。
ただ、じゃんけんじいちゃんとじゃんけんをしたかったのだ。
気が済むまでじゃんけんをしたら、僕はくるっと踵を返し子分が待つ家に戻る。
それが僕のルーティーンだった。
じゃんけんじいちゃんとの間に、特別な会話は必要なかった。
今思うと、じゃんけんじいちゃんは僕のことを待っていたのかもしれない。
そして、僕が住んでいたアパートの裏には、立派な一軒家が建っていた。
当時、幼かったからそう見えただけかもしれないが、バカでかい平屋。
そこには、子どもたちが寄り付かない怖いばぁ様が、多分ひとりで住んでいた。
僕は、ばぁ様を「おばあちゃん」と呼ぶとなぜか怒られそうな気がして「おばさん」と呼んでいた。
近所の子どもたちから人気のないおばさんは、なぜか僕には話しかけてくる。
本当は少し怖かった。
いや、かなりビビっていた。
でも、子どもながらに気づいていた。
このおばさんは、きっと悪い人ではない...と。
少し肌寒くなってきたある日、僕が子分たちを引き連れていつものように散歩をしていると、おばさんは僕らを縁側に招き、温かいお茶を飲ませてくれた。
ジュースがよかったな...。
そんなことを思いながら、小さな両手で湯呑を包み、ズズズッとお茶を飲む。
どこか所帯じみた雰囲気を醸し出している僕。
かじかんだ手と、冷え切った体がじわじわと温かくなる。
僕はお礼に、じゃんけんじいちゃんからもらった飴をおばさんにあげた。
完全に横流しである。
おばさんはうれしそうに飴を頬張っていた。
おばさんの家にはおもちゃがなく、妹は退屈そうに縁側でひたすら足をぶらぶらさせ、ベビーカーに鎮座するおまめは静かに天を仰いでいた。
僕は、おばさんとアルプス一万尺を永遠にした。
最近知ったが、実はアルプス一万尺は29番まであるらしい。
当時の僕が29番まで知っていたら、おばさんを楽しませるエンターテイナーになっていたに違いない。
ラーンラランラランランランラン♪
一見楽しそうにパチパチと手を合わせているが、この5歳児の心は躍っていなかった。
そしておばさんは、実はつまらない...と感じている僕の気持ちを見抜いたのだろう。
茶を飲み終えた僕らを、わざわざ家まで送り届けてくれた。
目と鼻の先なのに。
そして、僕らを無事に送り届けたおばさんは、なんと母に説教を始めたのだ。
何を言っていたのかは覚えていないが、
「こんな小さい子どもだけで外に出したら危ない」
そういうニュアンスのことを言っていたのだと思う。
仰るとおりだ。
母は何も言い返さず、シュンとしていた気がする。
そして、このときから僕は、おばさんを母をいじめる「敵」とみなした。
単純明快な僕は、この一瞬でおばさんが嫌いになったのだ。
さっきまでランラン言い合っていた仲とは思えない。
タダで茶も飲ませてくれたのに。
それから僕は、おばさんを見かけても、サッと逃げるようになった。
ときには電柱の陰からこっそり睨みつける。
母をいじめた仕返しをしたつもりでいたのだ。
僕の黒歴史。
おばさん、すまん。
そんなある日、じゃんけんじいちゃんが突然亡くなった。
幼い僕は、まだ「死」というものを理解しておらず、いつかまた会えると思っていた。
だけど、じゃんけんじいちゃんの家の前を何度通っても、僕を待つ人はいなかった。
じゃんけんじいちゃんのいない日常が、こんなにも寂しいなんて..。
僕の心にぽっかりあいた穴は、誰にも埋められなかった。
そして、じゃんけんじいちゃんが亡くなってから間もなく、僕らは隣町へ引越すことになる。
僕は、アルプスおばさんに「さよなら」も言わずに引越してしまった。
アルプスおばさんは寂しかったのだろうか。
恩を仇で返すような、定期的に睨んでくるガキがいなくなって、せいせいしたのだろうか。
今となっては、もうわからない。
そんな僕は、引越し先で新しい生活が始まり、アルプスおばさんのことを思い出さなくなっていた。
ピカピカの小学生になった僕は、初めて同年代の友達ができたのだ。
それはそれは、毎日が新鮮で楽しかった。
友達と遊ぶことがこんなにも楽しいことだったとは...。
きっと、初めてボール遊びを知った犬のようだったに違いない。
前方に歩いている友達を見つけると、通学帽のゴムをぶん回しながら
「一緒に帰ろぉぉぉぉぉお!」
と、走って駆け寄っていた。
母に何度ゴムひもをつけ直してもらったのか計り知れない。
大人になってから、僕が追いかけまわしていた友人に
「後ろから叫びながら走ってくるお前は恐怖だった」
と、カミングアウトされたときは、さすがに衝撃が走った。
何度も聞き返したが、紛れもない友人の本心だった。
僕は無意識に、友人へトラウマを植えつけていたらしい。
とにかく小学生時代の僕は最強。
測量士のトランシット(道端で写真撮影してるみたいなアレ)に向かって「イェーイ!」とピースしたり、友達とチャイムが気づかない場所で全力で遊んでいて意図せず授業をサボったりと、とにかくクソガキだった。
男女問わずいろいろな遊びをして、FTM特有の「おままごとや人形遊びが嫌だった」とかはなかった。
体を動かす遊びの方が好きだったけれど、遊べれば何でも楽しかったから。
おままごとで、ボス的存在の女子に犬役をやらされたときも全力で楽しんだ。
僕はワンワン言って、しっぽを振って喜んでいた。
幸いにも大人になってからその影響はないが、ときに子どもの遊びは狂気じみているとつくづく思う。
そんなある日、僕は友達と友達のお父さんとキャッチボールをして遊んでいた。
自分で言うのもなんだけど、僕は運動神経がよかったため、友達よりキャッチボールがうまかったのである。
そして、友達のお父さんは「うまいなぁ~!」と言って、僕の頭をなでようとした。
しかし僕は、反射的に頭をグローブでガードしてしまう。
殴られる...!と思ったのだ。そんな訳ないのに。
友達は不思議そうな顔をした後「なにビビってんだよー!」と言って、小学生特有のあのテンションで爆笑していた。
このとき僕は、あばれる君みたいな引きつった笑いをしていたと思う。
大人が大きく手を振りかざす動作が、とてつもなく怖かったのだ。
僕は、父親に頭をなでられた記憶がない。
殴られた記憶はいっぱいあるけれど。
「ごめんごめん」
友達のお父さんは笑いながら僕の肩をポンポンとたたいたけれど、この子何かおかしい...と思ったに違いない。
僕の反応は、きっと普通じゃなかったから。
そのとき、僕は気づいてしまったのだ。
この世に「優しい父親」が存在することに。
「父親」が、子どもの頭をなでる生き物であることを初めて知ったのだ。
友達が羨ましくてたまらなくなった。
同時に絶望を感じる。
僕は、皆が当たり前のようにもらっているものを与えてもらえていなかったのだ。
それから僕の知らない「当たり前」が、そこら中に転がっていたことに気づき始める。
誕生日ケーキに年齢の数だけろうそくを立て、吹き消す儀式をすること。
しっかり三角帽をかぶっているが、何も知らない僕は、なんで部屋真っ暗にするんや?とムードをぶち壊した。
友達の家にはサンタクロースが毎年来ていること。
うちには煙突がないから来ないんだ、と自分に言い聞かせた。友達の家にも煙突はないんだけどね。
飛行機や新幹線に乗って家族で旅行に行き、ホテルというところに泊まること。
僕は、自分の住む街のバスにしか乗ったことがなかったし、飛行機や新幹線は「大人の乗り物」だと思っていた。
家族で食卓を囲み、楽しい話をしたりバラエティ番組を見ながら楽しくご飯を食べられること。
こんなに楽しいテレビ番組があるんだ。ご飯ってこんなにおいしかったっけ?
お正月には、親戚からお年玉をたくさんもらえること。
僕は、親戚の顔も名前も知らなかった。
そして何より、言葉や暴力で危害を加えてくる人がいない、ということ。
いろいろなことに気づいてから、先の幸せな物語が見えなくなってしまった。
自分の家は「普通ではない」と思い知らされたのだ。
波平さんの「バッカもーん!!」には愛がある。
そんな愛を、僕は知らなかった。
「よそはよそ、うちはうち」というけれど、遥かにレベルが違う。
コイキングとギャラドスくらい違う。
家と学校だけの世界しか知らなかった僕は、絶望すら覚えた。
子どもからいろいろ奪うと大人が完成する。
僕はちょっぴり大人になるのが早かったのかもしれない。
だけど僕は、下の兄弟にそんな思いをさせたくなかった。
誕生日にはろうそくを立てたケーキでお祝いすることを教えてあげたし、なけなしのお金で好きなガチャガチャをやらせてあげた。
だけど、僕も精神的に限界が達し、いつからか兄弟に強くあたるようになった。
まるでお手本のような、Theキャパオーバー。
おそらく、鬱憤を吐き出す場所が兄弟以外に見当たらなかったのだと思う。
中高校時代の僕は、「普通」の家庭環境であることを演じるのに必死だった。
父に暴力を受けていること、家では常に怒号が鳴り響いていること、家庭内では笑顔より涙が多いこと。
絶対に友達に知られたくない僕の秘密だった。
友達に真実を知られたら、恥ずかしすぎて、情けなさすぎて、消えたくなる。
「とにかく明るいおもち」でいなければ、正気を保てなかったのかもしれない。
仲の良い家族に対して、強烈な憧れもあったのだと思う。
学生時代は、「家族」に対しても「性」に対しても、どうしても手に入らない「普通」が欲しくてたまらなかった。
セクシュアリティについては、なぜかオープンで堂々としていられたけど、家庭環境のことだけは、仲の良い友達にすら言えなかった。
最近になって、今でも仲の良い学生時代の友人にようやく真実を話せるようになった。
大体驚かれるけれど。
当時の僕の心は日に日にすり減っていき、成長とともに人とのかかわり方がわからなくなった。
自分の親とすら深い関係になれない僕は、ダメな人間なのかもしれない。
そんなことを考え、何度も何度も闇に引きずり込まれそうになった。
それでもしぶとい僕は、一歩手前で戻ってくる。
限界は突破済みで、謎の境地に入っていた僕は成人し、家族と離れて暮らすことにした。
実家を出るとき、
「お前、何も言うことはないのか?好き放題しやがって。誰が育てたと思ってるんだ。『今までお世話になりました』と言えぇぇぇ!」
と、父親に強要された。
...寝言は寝てYeah!!
なんだチミは。
そうです。あなたは「暴力」を「正義」と捉え、時代錯誤をしていた変なおじさんです。
この人は、一体僕に何をしてくれたのだろう...?
高校時代にバイトで稼いだお金は、学費・携帯代・定期代ですぐに消えて、遊ぶお金なんて、どこにもなかったよ。
でも、当時のマクドナルドは神だった。ありがとう、マクドナルド。
高校を卒業してフリーターになった僕は、家を出るために必死でお金を貯めた。
支援してもらうつもりは微塵もなかったから。
けれど、「頑張れよ」くらい言ってくれるのではないか?と、少し期待している自分もいた。
でも結局、励ましの言葉も金銭的な支援もなかった。
僕は一体、何に対して感謝をすればいいのだろうか。
精神的な耐久性を強くしてくれたこと?他人の顔色を伺うスキルを上げてくれたこと?
ことを荒立てたくない僕は「ありがとう」と笑顔で言い実家を出た。
そんなこと、1ミリも思っていなかったけれど。
それでも、この地獄から解放されるなら「ありがとう」のひとつやふたつ、安いものだ。
上辺だけの感謝の言葉なんて、いくらでも言えた。
僕は大嘘つきだ。
実家を出ても傷が癒えることはなかったけれど、不思議と心は安らかになった。
それから3年以上、僕は実家に寄り付かなかった。
ひとりで過ごす年越しも正月も、まったく寂しくなかった。
家族なのに、受け入れられない自分がいけないのだろうか。
置いてきてしまった弟や妹は大丈夫だろうか。
僕がまったく帰らないことで、母は父に責め立てられていないだろうか。
いろいろと自問自答をする。
本当は家族と一緒に、父から逃げたかった。
でも、当時の僕にはそんな度胸も経済力もなかったのだ。
安堵と同時に罪悪感が押し寄せてきて、黒い感情に飲み込まれそうになる。
そして、なるべく考えないようにしていたら、月日はあっという間に流れてしまった。
でも僕は、自分のことだけで精一杯だった。
誰も道を示してくれなかったから、人の愛し方も愛され方もわからない。
青年期の僕のメンタルは完全に笑っていた。
他人への期待は、時に絶望をより深くすることも知ってしまった。
そして、僕なりにたどり着いた答えは、
「許したくないことは許さなくていい。特に、謝罪もないうちは。」
だった。
自分を守るために、あのとき「逃げた」ことを、僕は後悔していない。
下の兄弟たちには申し訳ないと思ったけど。
でも結局、兄弟たちもそんな呪縛からは自分で抜け出さなきゃいけないのだ。
たくさんの重りがついていれば、歩くのは大変。
その重りをすべて取っ払ったとしても、結局歩くのはその人自身。
今、下の兄弟たちも無事脱出に成功し、それぞれ自立している。
一方で、危害を加えていた側は過去のことなど、すべて忘れているのだろう。
父は「ワシが育てた」と、思っているに違いない。
最低ラインの衣食住を提供してくれていたことには感謝するが。
やれやれだぜ。
被害者側は、一生忘れられないトラウマが残っただけ。
いじめと一緒。
「育ってきた環境が違うからぁ~好き嫌いは否めないぃ~」
山崎まさよしさんが言っていたけど、本当にそう。
いや、好き嫌いどころではない。
もちろん、劣悪な家庭環境で育った人はこの世にたくさんいるだろうし、他人と比べても意味がない。
でも、育ってきた環境が違うと、友達でもパートナーでも、どうしても埋められない溝がある。
夏が好きとかセロリが好きとか言いたいわ。
たとえばだけど、僕の兄嫁はサザエさんのような幸せな家庭で育った。(自分でもそう言っていたから本当にそうなんだと思う。)
兄嫁の当たり前と、僕たち兄弟の当たり前はやっぱりどこか違っていて、彼女と話していると僕はたまに卑屈になるときがある。
兄嫁が言っていることは頭では理解できるが、心がついていかないのだ。
現在、父と距離を置いている僕ら兄弟に「でも結局は家族でしょ」と言うのは、なかなかのパワーワードであり、酷だ。
「家族」という理由だけで、たくさんトラウマを植えつけた人のことを、自分を犠牲にしてまで大切にしなければいけないのだろうか。
そこに愛はあるんか...?
愛をくれなかった人にも、愛を与えなければいけないのだろうか。
僕のラブはプライスレス?
否!相手によって、料金が発生しますよ。
テストに出ます。
兄嫁の言っていることは何となく理解はできるが、どこか綺麗ごとに聞こえてしまうのだ。
家族でも所詮、他人は他人だ、と思ってしまう。
いや、もしかすると父と家族になれなかっただけなのかもしれない。
もし、自分が家庭を持つことができたら、この考えは覆されるのだろうか。
子どもができたら、どんなことがあっても愛し続けられるのだろうか。
幼少期の「当たり前」は、自分の根幹をつくっている部分もある。
だから、潜在的な部分はきっと変えられないと思う。
それでも、まぁまぁいい子に育った。
なぜか自己肯定感は強め。
ときに周りに「優しすぎる」と言われるのは、こんなバックグラウンドがあるからなのかもしれない。
だけど僕は、優しいのではない。
人の表情や雰囲気から、空気を読むことだけがうまくなった、ただの道化師だ。
それでも結果として、今楽しく生きているからおっけー。
生きていれば思いもよらない出会いもあって、歪んだ思考のクセも少しずつほどけていった。
世界が広いことを知り、視野もだいぶ広くなった。
だからといって、他人が裏切らないという保証はどこにもない。
誰も信じないで生きていけば、これ以上傷つかないで済むけれど、そんなのは寂しい。
心も、ひとつやふたつ傷つけば強くなるのだ。
だから僕は、誰かを愛し愛されたいと思う。
まぁ...パートナーいないんですけどね!
それでも、助けてと言える人がいる。
今はそれだけで十分だ。
昔住んでいたアパート一帯は区画整理され、当時の面影は1ミリも残っていなかった。
今思えば、「じゃんけんじいちゃん」や「アルプスおばさん」は人情深くて、波平さんやフネさんみたいな人だったのかもしれない。
もう、会えないのだけれど。