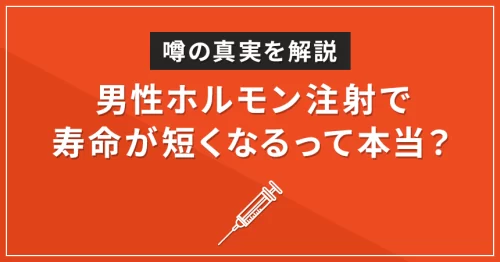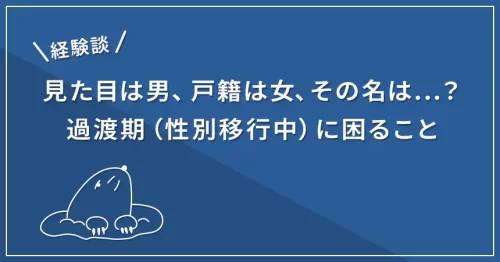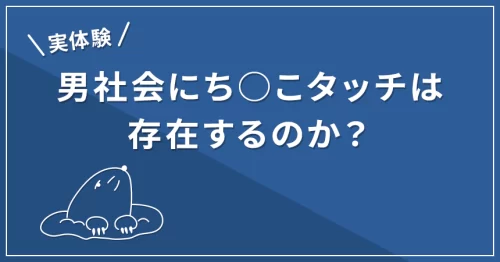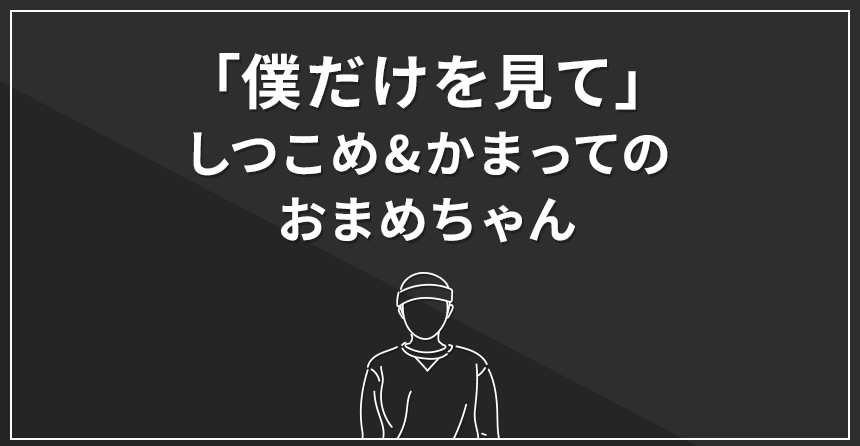
こんにちは、おまめです。
僕は幼いころ、兄や姉から「しつこい。」と言われることが多かった。
しっかり無自覚である。
当時のボキャブラリーが少なすぎる僕は、いいよと言ってくれるまで同じ言葉を連呼する。
「おもちゃ貸して。おもちゃ貸して。おもちゃ貸して…(まだまだ続く)」
おそらく母親にもしつこいと思われていたと思う。
当時の僕たちの日常を、母親がカセットテープで音声録音していたデータが残されている。
兄弟が楽しく話す中、僕は永遠と連呼していた。
「おかーしゃん、あっこ(だっこ)してよ。あっこしてよ。あっこしてよ…(まだまだ、まだまだ続く)」
最初に聞いたときは、「ん?テープ…バッグってる?」と思った。
しかしテープではなく、しっかりと僕がバグっていたようだ。たまげた。
僕は、保育園や幼稚園に行っていなかった。
え?そんな人いるの?
そう驚かれることに、僕の方が驚いた。別に普通だと思っていたからだ。
就学前の僕の世界は狭かった。
外に出るといえば、家から自転車で3分ほどのスーパー。
母は決まったものを買い、僕は得意げに荷物運びを手伝う。
それ以外、外に出ることはほとんどなかった。
兄姉は学校に行っているため、遊び相手はいない。
おえかき、ぬり絵、ひとりオセロ、ひとり将棋...。
録画したジブリのビデオは、画面がシャシャシャってなるくらい、すり切れるまで観た。
それゆえに、ジブリの中でも特に大好きだった「となりのトトロ」と「天空の城ラピュタ」は、冒頭からセリフをほぼ丸暗記して、同時にセリフを話していた。恐ろしい景色だ。
僕が4歳のとき、弟ができた。
当時の僕は、どうしても弟のことを好きになれなかった。
お母さんを取られてしまう...。そう思ったからだ。
そして、実際そうだった。
「かまってちゃん」の僕はこの時に、しつこくするだけではイラつかせるということを、理解したのである。
これを幼少期に覚えられたのは良いこと。しつこい男は嫌われるからね。
「なるべくいい子にして、母の隙をみて構ってもらう」作戦に変更した僕は、構ってもらえない時間は、じっとひとり遊びを続けていた。
母が何をしているか日々観察する。作業の合間が狙い目である。
合間につかさず構ってとアプローチする。
2日に1回くらい、母は一緒にオセロや将棋をしてくれた。
ミジンコみたいな脳みそで立てた作戦は、無事成功したのだ。
でも、1日1回だけ。
それが、母と僕の暗黙のルールだった。
楽しくて「もう1回!」と、無邪気にはしゃぐ僕。「ごめんね」と言って、去っていく母。
試合に勝って勝負に負けた。
僕はまたひとりオセロを始める。
そんな僕は、母に構ってほしい一心で、毎日お手伝いをしてポイントを稼いだ。
お手伝いをしながら、大好きな母を毎日観察する。
大量の洗濯物、子どもたちの世話、買い物、ご飯の支度...母は1日を終えると、倒れ込むように眠った。
そしていつの間にか、僕はわがままを言えなくなっていた。
夕方になると、小学生の兄や姉が帰宅する。
ランドセルを投げ捨て、遊びに出かけるおもちを、短い足で必死で追いかけた。
おもちの友達に混ざって、サッカーや鬼ごっこをする。
僕は、みんなの輪に溶け込んでいる気満々だったが、今思えば小学4年生と4歳。
相手になどされているはずがない。それでも楽しかった。
外で遊べるだけでうれしかったのだ。
鬼が追いかけてくれないと、かまってちゃんの僕はすぐに飽きる。
そして、ひたすらダンゴムシをポケットに詰め込む。
おもちはそんな僕を一瞥して、見ないフリをした。
当時、小学生の間でBB弾が流行っていた。
大量にちらばっている玉を拾って、兄に渡す。
すると、信じられないくらい褒めちぎってくれる。
ダンゴムシを渡したときは、本気で怒られた。
自分の背丈以上ある草むらにサッカーボールが消えたときは、率先して探しに行く。
どや顔で「あったよ!」と言うと、またもや兄たちは褒めちぎる。
完全に利用されていた。でも、それでいいのだ。
唯一、自分に注目が集まるタイミングだったから。
それが最高に気持ちよかった。
誰かに構って欲しい。僕を見て欲しい。
承認欲求強めの小さな塊だった。
家に帰ると、夜ご飯の準備を手伝わなければいけない。
先にキッチンにいるおもちを真似て、僕も手伝う。
チビだった僕は、邪魔モノ扱いをされ、結局ひとり遊びを始める。
そうしているうちに、ガチャっと玄関の開く音がする。
その瞬間、さっきまで賑やかだった家の雰囲気が180度変わるのだ。
父...王の帰還だ。
おかえりなさい...
誰かが必ず玄関まで出迎えなければいけない。
父が荷物を置いて、食卓に座るまでにグラスに半分氷を入れ、お酒と割りものをセットする。
我が家のマニュアルだった。
父は、氷が溶けてなくなると「氷」と、ひと言だけ発する。
誰かが必ず立ち上がり、取りにいかなければいけない。
何か作業をしていても、王の言うことは絶対なのだ。
王の機嫌を損なってはいけない。
王様の言うことはー?ぜったーい!だった。
箸の持ち方がおかしいと、3歳でも容赦なくぶん殴る。
上の兄弟が殴られているシーンを数えきれないくらい見てきた僕は、世渡り上手になった。
どうすれば殴られないか、だけを考えて生きていた。
上の兄弟の失敗を見て、いろいろ学ぶ。父の顔色を常に伺っていた。
それでも機嫌が悪いと、意味もなく殴られた。
兄弟で遊んでいるだけで「声がうるさい」と言って殴る。父が家にいる時は、ひそひそ声で話さなければいけなかった。
夜が怖かった。
はしゃいでいると確実に仕留められるため、夜ご飯を食べた後はおもちが読み書きを教えてくれた。
食後のお勉強タイムだ。
おかげ様で、保育園や幼稚園には行ってなかったけれど読み書きができた。
おもちは、手書きで作成したテストを出してくれる。
問題が解けたら、おもちのところに持って行く。赤ペン先生ならぬ、「赤ペンおもち」が丸つけをしてくれた。
おもちがつけてくれるハナマルやシールは、飛び跳ねるほどうれしかった。
おもちも、べた褒めしてくれる。
答案用紙を握りしめ、4歳児は自慢げに母に見せにいく。
「すごいね~。」
洗い物をしている母は、僕の顔も答案用紙も見ずにそう言った。
それでも僕は大満足だった。
今思い返すと、僕はおもちに育てられたという感覚が強い。
きっと、姉もその感覚が強いはず。
ケガをして泣きわめいたときも、9歳のおもちは僕を背負って5階まで階段で登り、僕をせっせと運んでくれた。
しかし、だんだんと階段を昇るペースが遅くなっていく。
僕より辛そうになっていくおもちの背中に、ずっとしがみついていた。
本当は歩けたのだけれど。あまりにも居心地がよかったもので...。
そんなことを知らないおもちは、必死すぎる笑顔で僕に「大丈夫だよ!」と声をかけ続けていた。
あの横顔は忘れない。肩で息をしていた。
ごめんね、おもち。
親に甘えられない分、おもちに甘えていた...いや、甘えすぎていたのかもしれない。
そんなかまってちゃんの僕も、小学校にあがると友達ができて、放課後は毎日のようにサッカーに明け暮れた。
おもちは中学生になり、わかりやすくグレた。
髪の毛も金髪にしちゃってさ。こっわ。
中身も、人が変わったかのように意地悪クソ野郎になった。
そうでもしないと、異常なこの家では正気を保てなかったのだと思う。
そんなグレたおもちを、父は首根っこを持って引きずり回していた。
まさに、大乱闘スマッシュブラザーズ。
止めに入る母は力が及ばず、気づいたらコロンと吹っ飛んでいた。カービィーとかプリン系の吹っ飛びやすいタイプなのかな。
恐怖映像すぎて、姉と僕はワンワン泣く。
そして、泣く声もうるさいと怒鳴られる。
父の怒りの矛先が僕たちに向かないよう、怒号や悲鳴が聞こえないよう、姉とふたりで真っ暗な布団の中でシクシク泣いた。
僕が小学校中学年になると、母はパートを始めた。
今思うと、母は家だけじゃなく、外にもコミュニティができて本当によかった。
母が忙しいときは、自転車で10分くらいの保育園へ僕が弟と妹を迎えに行く。
9歳の僕がママチャリに跨り、前に1歳、後ろに5歳を乗せる。さすがに無理なので、5歳を走らせる。
当然だが、保育園の先生に母は注意された。
それからは歩いて迎えに行くようになった。徒歩30分弱の、なかなかハードな距離。
手をつなぎながら、土手沿いを歩く。今日の楽しかった出来事を無邪気に話す弟と妹。
半分くらい何を言っているか分からなかったけど、そんな時間も今となっては宝物だ。
僕たちは、こうして逞しく生き抜いてきた。
おもちが高校生になると、僕の精神年齢もグッとあがり、いつからかマブダチになった。
バイトで夜遅く帰ってくるおもちを、首を長くして待つ。
顔にラクガキしあったり、全身タイツ履いたり、ストッキングかぶったり。
結構ハードな、しょうもない遊び。楽しかったな。
まるで家の問題を笑い飛ばすかのように、くだらないことでケタケタ笑った。
ちょうどこの頃、おもちはひとり暮らしをすると言い始めた。
当時の僕は中学生。マブダチだから連れてってくれるだろう。
いつも僕を助けてくれるおもちだ。
僕を見捨てるわけがない。こんな家に、僕を置いていくはずがない...。
本気でそう思っていた。
あり得ない話だと、今ならわかる。
20歳なんて、ひとり暮らしをするだけで精一杯だ。中学生を連れて行くはずがない。
そして、ついにおもちは僕を置いて去っていった。
裏切られた...。
心の底からそう思った。同時に、嫌な予感もしていた。
その嫌な予感は的中し、おもちは数年間、音信不通になった。
年末もお盆も帰ってこない。
メールを送っても、返信はなかった。
僕のことまで嫌いになったの...?
当時はめちゃくちゃ悲しかった。
おもちが去ってから、思春期も相まって、僕も180度変わってしまう。
だけど、金髪にはしなかったし、グレてもいない。
誰とも話さなくなったのだ。
あんなカマッテ星人だった僕が…信じられない。とことん無視を決め込むタイプのアレ。
そして高校では、何かに憑りつかれたように部活に打ち込んだ。
朝5時に起きて、自分で弁当をつくり、家を出る。夜の9時に帰宅し、できるだけ誰とも顔を合わせないよう無言でご飯を食べて部屋で寝る。
しかし、タイミングが悪いと父に鉢合わせた。
ベロベロに酔った父。
「遅くまで遊んでんじゃねぇ」「金稼いで来い」「その目つきはなんだ」
きっと、理由など何でもよかったんだと思う。
そして僕は、大人なんて信用できん!&無の境地に突入。
かわいがっていた弟や妹も、完全にシャットアウトした。
ドアの隙間からこっそり覗かれているのも気づいていたけど、とことん無視した。
そして母は、部活は続けて欲しいと言った。
なんとか続けてはいたが、同じ部活の友達が恵まれた環境で育った子が多かったことも、僕を苦しめた。
朝寝坊して、自分で弁当をつくれなかった日は、僕のお昼ご飯は菓子パン1個。
腹を空かして、目を血走らせながら死ぬほど走った。
友達の目に、僕はどう映っていたのだろうか。
こんな状態で部活を続けろって、親のエゴだろ...という怒りも沸いた。
結果的に、部活は続けていてよかった、と思う。
やめていたら、道を踏み外していたと思うから。
さんきゅーマザー。
そして、大学進学を機にひとり暮らしを始める。
奨学金を借りてでも、大学に行く道を選んだのだ。大学は、家から通えない場所をあえて選んだ。
理由はいろいろあったけど、とにかくこの家から逃げたかったから。
学費は自分で払うことになったが、さすがに入学金などの資金は援助してもらった。
父は、お金を出すのが嫌な人ではない。
「俺が大学に行かせてやった。感謝しろ。」
つまるところ、そういうことだ。
しかし、大学3年になるタイミングで大きな決断をする。
実家に戻り、2時間半かけて通学することに決めたのだ。
理由はいくつかある。
まず、ホルモン治療を始めるタイミングだったこと。変化の過程を、親に見せるべき...?と思ったのだ。
そして何より、弟と妹が心配だったから。
ひとり暮らしを始めてしばらく経ったころに、僕が実家に立ち寄ったときのこと。
かわいかったはずの弟と妹が、変貌を遂げていたのだ。
おもちがいなくなって、荒ぶっていた僕のように。
え、待って。誰?僕、そんな子知らんよ...。
無邪気に笑っていた妹は、人の顔色を伺う仲裁上手な大人子どもになっていた。
弟は、僕と同様、無視を決め込んでいた。そんな状況を見てみぬフリはできなかったのだ。
1度は逃げたけど、今の僕だったら何か変えられるかもしれない。
なぜか妙な自信があった。
だが、この選択が間違いだったとは、このときの僕は知る由もない。
意を決して2年ぶりに実家に帰ると、大きく変化していたことがあった。
それは、父が物理的な暴力を振るわなくなっていたこと。
年齢のせいなのか、孫レベルで年の離れた我が子をかわいいと思い始めたのかはわからないが。
しかし、言葉の暴力が誰に対しても加速していた。
あと、声もデカくなっていた。これはもう、手に負えん...。
むしろ、僕が家に帰ったことで火種がわんさかできてしまった。
しゃあない。僕が大人になろう。
一世一代の決心をする。
僕は一生懸命、父に寄り添おうとした。
酔って何度も話す、父の若かりし過去の栄光トークも、笑顔で聞いた。機嫌よく話していたと思ったのに、酒が一定量に達すると、父はいきなり暴れん坊将軍になる。
ぶっ壊れたおもちゃみたいだった。
翌日、父は何もかも忘れていた。
僕と話をしたことも、お馬さんに乗っていたことも。
白旗を立てるしかない。
そんな環境で育った僕たち兄弟は、父の血を引き継いでいるのか酒豪である。
不幸中の幸いで、酒癖の悪い奴はいない。
僕は社会に出て、いろんな人と関わり、いろんなものを見てきたが、あの家はやっぱり異質だった。
それでも今、地に足をつけて生きていることが何より幸せだ。
他の兄弟も然り。
それを感じられて、よかったと思う。
割といい子に育ったと自分を褒めたい。
今でもおもちにまとわりついて「しつこい」と言われることはあるのだけれど。
それもご愛嬌。